最近では、『美容男子』という言葉が出来るくらい、美容に意識を持つ男性が徐々に増えつつあります。そんな中で大西流星さんがメイクでTikTok大バズリ!
そのかわいい顔のメイク男子・大西流星さんが、『ウソかホントかわからない やりすぎ都市伝説』に出演するので調べてみました!
みなさん一緒に見ていきましょう!

引用元:Instagram 大西流星/Onishi Ryusei(08.07_ryuche)
大西流星プロフィール
名前
大西 流星(おおにし りゅうせい)
「流星(りゅうせい)」という名前は、生まれた日がしし座流星群の見える日だったことに由来してます。
生年月日
2001年8月生まれ
出身
兵庫県西宮市
大西流星のそのかわいい魅力
大西流星さんと言えば、そのかわいい顔がとても魅力的です。なにわ男子の中でも随一の可愛さを持っていると、デビュー前からファンの間で話題になっていました。
大きくて綺麗なくっきり二重の瞳
なにわ男子きってのあざとかわいい「りゅちぇ」こと大西流星さん。
大西さんは、その大きくて綺麗なくっきり二重の瞳が印象に残ります。鼻筋も通っていて綺麗な顔立ちの印象ですよね。
そして、自分の見せ方の研究もしているそうで、1年間あざとい女性を研究してきて、それを知った田中みな実さんから「あざとくて何が悪いの?」の番組にオファーされてしまうほど研究熱心なところもあります。
プロ意識を高く持っているエピソードですよね。
メイク動画でTikTok大バズり
あざとかわいいを追及している大西流星さんが、TikTokで大バズりしたメイク動画があります。
その動画は、公開から1か月足らずで約300万回再生を記録しているというもの!
慣れた手つきでメイクをして、ポイントになるところを解説してくれるというもの。これには、コメント欄で賞賛や共感、リクエストの声が続出しています。
大西流星プロデュースコスメ
大西流星さんは、2022年11月化粧品ブラントのエテュセとコラボレーションコスメをプロデュースしました。
“瞳全体がきれいに見える”をテーマに、アイメイク4アイテムとリップアイテムの全5アイテムを販売し、SNSでも大きな話題になりました。
中学生の頃からメイクに興味
中学生の頃からメイクに興味があった大西流星さん。
メイクの魅力について「(メイクをすると)モチベーションを上げてくれる。新しい自分に出会うことができるので、自分の心さえも高揚させてくれる」と話していました。
また、「この時代で“自分らしさは何なのか”って考える機会って多くなってきたと思うんですけど、“メンズだからこうあらなきゃいけない”っていうのもないと思うし、それをみんなが受け入れるような世界になってきたのかなと思うので、それで自分に自信を持てればそれでいいんじゃないかなって。
その気持ちがたくさんの人に伝わって、今まで躊躇(ちゅうちょ)していた人たちも、自分らしく我慢せずに生活できる世の中になればなと思います」と笑顔で話しています。
メイクを通して「自分らしさ」を追及している大西さん。
中学生から大切にしていた「メイク」が、自分らしさなんだとTikTokで伝えてくれたのかなと思いますね。
年々メンズコスメの市場規模が拡大している
男性の間でも、年々「美容意識が高まる」傾向にあり、コロナ渦のステイホーム中に美容への意識が高まったと言われています。
『美容男子』といえば、若い10代後半から20代の男性がイメージできるかもしれませんが、コロナ以降より『顔の衰え』を実感された30代から40代の方の男性も増えてきているとのこと。
今までは女性のものという意識が高かった『脱毛』や『メイク』や『スキンケア』などが、現在では『メンズ専門』などの名前が付くスキンケアコスメや、サロンが多く目につくようになってきています。
”美容男子”について女性はどう思っているのか
美容に気を使っている”美容男子”について、女性はどう思っているのか?調べたところ、大半の女性は
「いいと思う」や「ある程度なら」という肯定的な意見が多いように見られます。
否定的な意見は少数であり、いきすぎた美容意識でなければ、多くの女性が「美容男子」を好意的に受け入れてくれるようです。
日本のメイク男子の歴史
「メイク男子」と今は言われていますが、ひょっとしたら昔から日本では「お化粧をする男性」はいたのではないかと思い、調べてみました。
武士も貴族もみんなしてた?男の美学が宿るメイク男子の歴史
古代日本においては、男女問わず赤化粧(丹塗り)の風習がありました。
顔面はもちろん、全身に赤い色を塗る化粧の風習は、日本のみならず世界各地に存在しており、赤は太陽の恵みや魔よけなどの意味を持っていたと考えられています。
当時の日本では支配者に対する“服従”や“恭順”の意味でメイクをしていたようです。
平安時代男性にも広がった白化粧
平安時代、貴族女性の間で行われていたのは、眉化粧。
自眉を毛抜きで抜いて白粉を厚く塗り、太い眉を描くというものです。歯には鉄漿(おはぐろ)を塗り、唇に少量の紅を指していました。
この日本独特のメイク方法は、平安時代後期には男性の間にも広がっていきました。
清少納言著の『枕草子』にも「白化粧がムラになって見苦しい」と男性のメイクについて言及する記述があり、眉化粧が男性においても身だしなみの一つとして定着していたことがうかがえます。
赤化粧から白化粧に変化した理由には諸説ありますが、肌をキレイに見せることができたなどの理由が挙げられています。
平氏もメイクしていた!
武士も、実はメイクをしていたということは意外と知らない方も多いのではないでしょうか?
武士で最初にメイクを取り入れたのは、源氏とともに勢力を二分していた平氏。
平氏は政治の実権を握りますが、その際貴族の生活スタイルを積極的に取り入れていきました。その一つがメイクです。
彼らのメイクは、平安時代からの流れを受け継いだ貴族風の眉化粧。威厳を保つ意味もあったと思われます。
秀吉もメイクしていた!?
武士の間で平氏が敗れた後、メイクは一時途絶えましたが、室町時代になると復活。再び貴族をまねてお歯黒をするようになります。
そのメイク熱は、戦国時代に入っても続き、今川義元や北条氏綱・氏康などが貴族風のメイクを取り入れていたのだそう。
平氏と同様首を取られても武士としての誇りを保つため、教養や地位の高さを示すため、また公家文化への憧れなどが理由として挙げられています。
豊臣秀吉の伝記『太閤記』では「作り鬚(ひげ)に眉を作り、鉄黒(おはぐろ)なり」という記述があり、秀吉も晩年は公家風のメイクをしていたようです。ちなみに、戦国時代のメイクは大将など身分の高い武士を中心に行われていました。
江戸時代、身だしなみは粋な『江戸っ子』の条件だった
江戸時代は、今まで上流階級だけのものだったメイクが、歌舞伎役者や遊女といったインフルエンサーの影響で町人の間にも普及。
化粧水や白粉などのコスメが人気を博し、美容本『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』がベストセラーになるなど、空前の美容ブームが巻き起こりました。
一方、武士のメイクは衰退傾向に。
公家や歌舞伎役者を除いた男性の間ではほとんど行われなくなったものの、武士道を説いた名著『葉隠』では、武士に身だしなみの一環として口紅や頬紅を持ち歩くよう推奨しているので、一部の武士の間ではメイクの習慣が残っていたようです。
紅や白粉を使ったメイクをする機会は少なくなりましたが、男性も身だしなみには気を遣っていました。
天明年間(1781年~1789年)には、町人の若者の間で眉のお手入れがトレンドに。眉を抜いて薄くした“かったい眉”と呼ばれるスタイルで粋を競っていたのだとか。
明治から現在
古代から江戸時代にいたるまで、男性もさまざまな形でメイクを嗜んできました。
この長い歴史にピリオドを打ったのが、明治維新です。
その後、昭和の大きな戦争を乗り越えて社会が安定してくると、再び中性的なスタイルが特長の“フェミ男”や、派手なメイクを楽しむ“ギャル男”などが若者の間で流行しました。
そして、今のメイク男子ブームに繋がってきています。
まとめ
自分らしさとは、と悩んでいた時期もあったという大西流星さん。
メイクを通して「自分らしさ」を発信して、彼の魅力をどんどん広げていってほしいと思いました。

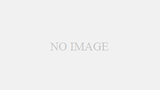

コメント